
今回は結構やってしまいがちなリアリティのない台詞の話し方についてお話しいたします。
今から申し上げることは無意識に台詞を話そうとするとどうしてもやってしまいがちになるので、特に演劇の初心者の方々には是非参考にして頂ければと思います。
さて、本題に入りますが、
やってしまいがちなリアリティのない台詞の話し方とはどういう話し方か?
それは……
次の言葉があたかも分かってるかのようなセリフの話し方をしている
ということです。
普段の私たちの会話は、このくらいの長さで話そうなんて考えてないですよね。
でもセリフが用意されていると、例えば、自分のセリフが台本に5行あれば、その5行の話の組み立てで話をしようとしてしまいがちになるのです。
あたかも次の言葉があるのを用意しているかのような話し方になるので、リアリティがなく違和感のある会話になってしまう。
普段の私たちの会話は、相手の顔色を伺って話をします。自分の話していることが伝わっているかどうかは話している人にとっては重要な情報なので、相手の理解度によって、言葉を変えたり、考える間を作ったりをその場その場でしている。
基本は次に何を言うかはその話している本人にだって分からないことの方が多いのです。
ただもちろん例外はあります。何かを教えている人や、説明している人の中には、予め自分の得意な論法で話を進めるため、相手の顔色を伺わなくても理解できるであろうと決めて話す人もいるので、一概には言えません。
ただ、こういう論法で話す人は、相手に詰め寄る際に使ったりすると、相手に問答無用という立場で話が出来ているので、それはそれでまたリアリティのある表現にはなります。
普段の会話では、やはり次にどういう言葉が出てくるのかというのは本人にも分からない方が自然なのです。
しかしながら、舞台に上がると決められたセリフを話すわけで、相手がこれを言えば理解するのは当然だからと、相手の顔色もうかがわずに話してしまうという傾向が多く見えます。
もし仮にですが、
決められたセリフを全く意図の違った話し方をされると聞く側はどうなるでしょうか?
聞いた人も当然ですがそれに応えるセリフがあるのでやむを得ずそのセリフを話はしますが
違和感は残ってしまう。
そう言われると自分の言いたい意図で言えなくなるんだよな~
となります。
聞く側の人間に何か違和感がある場合、その違和感は無意識に観客にも伝わります。
だけど、難しいのは、これを無意識に感じているから、何かおかしいと思ってもそのままセリフを受けて続けてしまうところがあるのです。
こういう意図のかみ合ってない、いわばボタンの書き違えた会話も台本という決められたものがあると、形上は成立してしまうのです。
そしてもっと怖いのが、稽古を重ねるとそれがおかしいと思わなくなってしまうということが起きてしまうということです。
毎回やってると慣れてきて違和感すらなくなってしまうのです。
これは
自分たちの不安を取り除くためにしているような稽古
になってしまっています。
ですので、どうしてもこの違和感をなくすことが大切なのです。
この違和感をなくすためには、セリフの話し方をもっともっと知る必要があります。
ですから、今回、聞いている人にも違和感のないように話す台詞の話し方をご紹介します。
それは、
自分の息でセリフを話さないということです。
飽くまでも、自分自身がセリフを話そうとする息ではなく、役の人物の衝動で身体が動き、その中の息で話すということを心掛けるということです。
例えば、苦しんでいる人の台詞の例で……
まず、
句読点は、セリフを話しやすいようにするためのブレスでは決してありません(笑)
台本に書かれている句読点は、息を吸わずに間だけを空けたり、変調するためのものや他にも様々な使い方をするものです。
そして苦しい芝居をする場合は息の少ないところで話をすると「緊張感を生んだり」「苦しい」「窮屈」が表現として伝わるのでそのように話します。
どうして息の少ないところで話をすると苦しいのが伝わるのか???
それはこういうことです。
よく映画で登場人物がピンチの時に海で潜水するシーンとかありますよね。
あれを見ている人は登場人物と同じように息を止めて見てしまうのです。これは物語の中に入り込んでしまうと無意識にそうなります。
つまり、登場人物を同じように苦しくなってしまうのです。
ですから、それと同じように、苦しい表現の時に息のないところで声を出して話をすると見ている人も間違いなく苦しくなるのです。
その苦しい台詞の中に句読点があって、ブレスなんかいれようものなら……
まだまだ余裕があるじゃん
って無意識に感じてしまうのです(笑)
これが無意識の違和感というものなのです。
苦しそうに話しているけど、なんか苦しそうに見えないんだよな…
こういう風にセリフを話している人は実は結構多いのですよ。
後は、セリフを下から上にしゃくるような話し方であったり、同じ3つ言葉のセリフが続いた時に一段階二段階三段階に分けて徐々に上げていく話し方であったり、本当に色々と言うこと決められているのがこれらはすでに分かっている話し方であり、用意されたものと感じてしまってリアリティがなくなるのです。
抑揚や強弱をつければ自分の気分が乗ることもあるでしょう。
しかしそうやってリアリティとは逸脱した抑揚や強弱をつけてセリフを話すと間違いなく浮いてしまいますし、おそらくですが演劇アレルギーの方はこの辺がとても気になるところなのではないかと思います。
何だか分からないけど、無駄にテンション高いね
こういう演技を見てしまうと、作品に入るのはおろか、逆に不快感を募らせてしまうのです。
どうして、不快感を募らせてしまうのかというと??
自分勝手な演技を押し付けられている
と無意識に感じるからです。
ですので、お芝居は限りなくリアリティを追究し、それに則った表現でなければいけないのです。
リアリティに則った演技というのは、お客様に対するおもてなしの表現です。
お客様が自然に作品の中にすっと入って頂くための重要な演技なのです
それをまず知らなければ、いくら考えられた表現が出来ていたとしても、お客様は決して意図通りにはご覧にならないでしょう。
最後に重要なことを。
本当はですね。
違和感というものは、セリフを話している本人が一番最初に気がついているものなのです。
だけど、どうセリフを話して良いか分からないため、探りながら探りながらセリフを発していくうちに、やがてその違和感が慣れから消えてしまっているのです。
本当に違和感なくしっくりきているセリフを話せていたならば、当然ですが聞き役の相手の心にもすっと入ってくるものなのです。
本当はそういう仕組みがあるのです。
その仕組みの中にちゃんと自分たちがアプローチできていないのですね。
違和感を作り出しているのは自分自身でその違和感を解消するために練習を重ねてその違和感を消そうとしているだけなのかもしれません。
少し厳しい意見に聞こえるかもしれませんが、お客様の目はもっと厳しいものだと思っています。
そういう厳しい目と勝負しなければ、演劇の前途は明るいとは言えないかと思います。
演技はまずその技術を知ること。そして、その技術を見るための目を養わなければなりません。
素晴らしい俳優の演技は素晴らしい俳優にしかその技術は分からないものです。
これからを担う方々に、出来るだけ早くこのことを知って頂いて、今よりも素晴らしいものを創造して頂ければと切に願います。

さいとうつかさ
劇団ブルア 代表
劇団道化座に13年間所属し、日本各地、海外公演に数多く出演。道化座退団後はフリーで演出・俳優活動を行う。「社会に寄り添う演劇」を掲げ、2019年に劇団ブルアを設立。同劇団代表を務める。現在の演劇活動として、演出業、俳優業だけではなく、関西各地で演劇のワークショップで演技指導も行う。出演回数は400ステージを超え、実践的な演技指導が持ち味。またスタニスラフスキーシステムを独自にアレンジしたブルアメゾッドを作り、「身体動作から感情を誘発させる」演技術を展開し、リアリティーのある演技を追究。「役の人物を介して自分を表現する」「自己探求」などを念頭に演技向上を図り、ありのままの魅力的な自分で勝負する独特の演技コンセプトが好評を得ております。
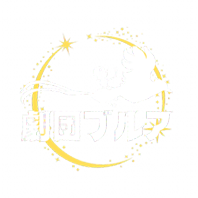
「セリフを話す時の落とし穴1」への1件の返信