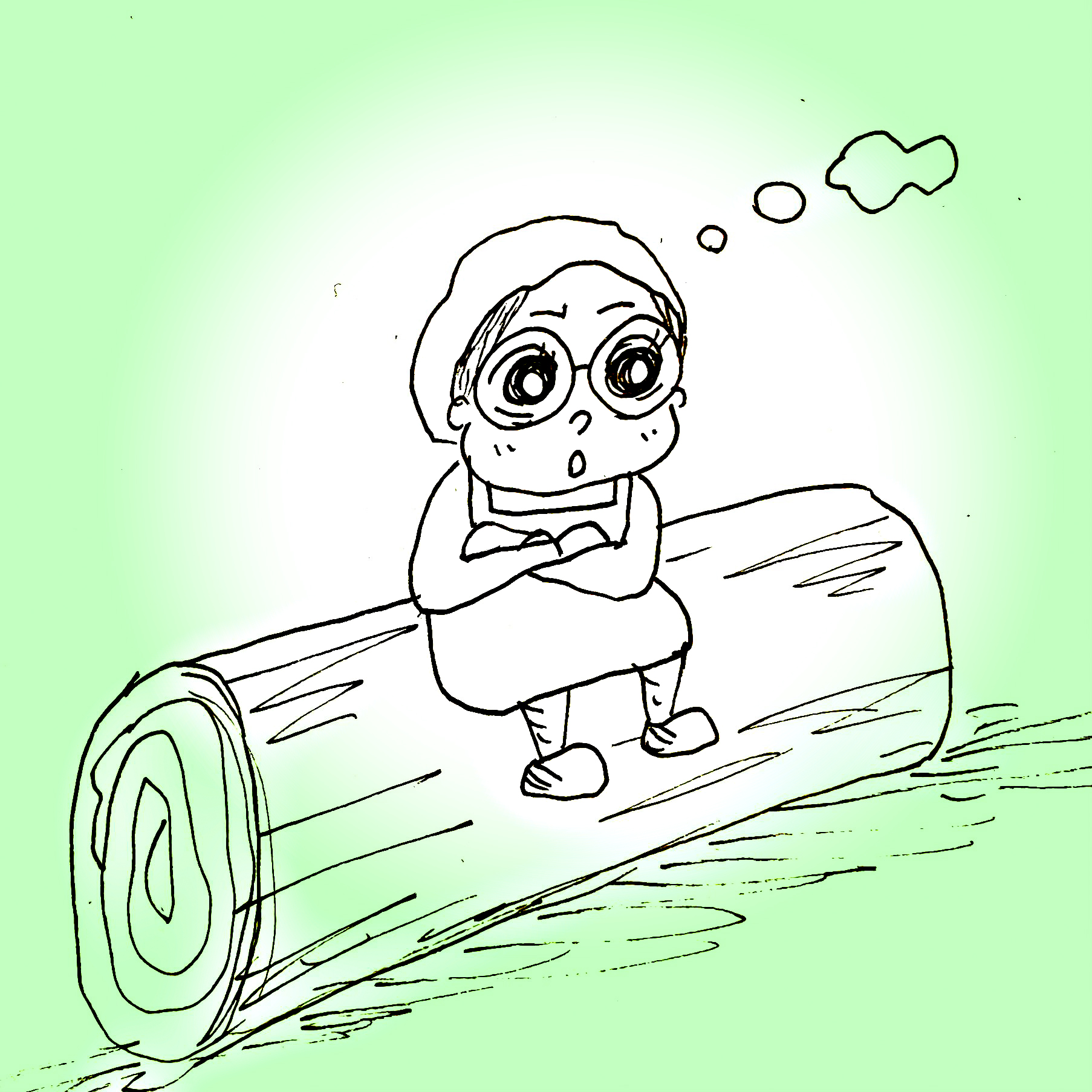
多くの演技者は台本を貰うと自分の台詞があるところを意識します。これは、まず第一のタスクとして自分のセリフを覚えるということがあるからだと思います。この意識が悪いというわけではないのですが、自分のセリフだけのところを見ると主観的なモノの見方だけになりがちなので、全体的な視野で見るためにも自分以外のところも見る意識もやはり当然必要になります。台詞は自分の言っていることも決まってますが、相手の言うことも勿論決めらているので、
相手の言いやすい台詞渡しをすること
がとても重要ですよね。「自分はこのように言いたいから」と言って、相手の応えるセリフと合致しないやり方をしていると当然嚙み合わなくなりますし、噛み合わなくなるということは、ゆくゆく自分にとっても気持ちの乗れないしんどい稽古となるのですね。ですので、相手のセリフもよく吟味して自分のセリフを練ることが必要になるのです。
しかし、実はそういう読み方のほうが、客観的に見られて自分のセリフの話し方の方向性が見えたりするのです。この時に、自分のセリフを覚えると考えると、相手の台詞もしっかりと吟味するのはどうも手間がかかると思うかもしれませんが、実は自分のセリフの方向性を決めるのに一番手っ取り早いのがこの方法なので、相手の台詞をまずしっかりと読み込むことがとっても重要なのです。こうすると、「相手はこうしてあげた方がやりやすいかな?」ということも分かってきますので、ホスピタリティのある演劇が出来るようになるのです。そして、相手の為に動ける演技を考えられている集団はとても素晴らしい作品を作り上げていきます。どうしてかというと、相手の良い部分を引き出そうとする行為に繋がっていて、相乗効果が生まれるからです。
簡単に言うとそういうことですが、相手が自分の為に芝居をしてくれていると考えると期待に応えたいのが人情です。そういう心が演劇を良くするエネルギーを生み出し、自分の力以上のものが発揮できるということなのです。ですから明日からは、
自分のセリフに蛍光ペンを引くのはやめましょう(笑)
蛍光ペンを引くことによって引いていない部分がスコトーマ(心理的盲点)になって、相手との調和を図ることが難しくなります。既に引いちゃったよという人は、ト書きも含めて相手の台詞も全部引きましょう(笑) まぁ、それは冗談ですが、稽古が佳境に入ってきた時に、
あ、こんなことが書かれてあった…
というようなお粗末な読み方にならないように工夫していければ良いですね。さて、本日のお題、
色んな身体の動きで「伝わる」演技を
ということですが、今回はお客様へというわけではなく、共演者へ「伝わる」演技をするというお話を次のページから致します。
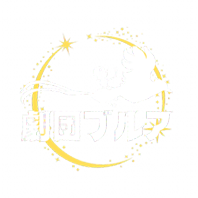
蛍光ペンに関しては分かりやすくするために
人物ごとに違う色のを引いたりするのが良いんですかね、
すべてが同じ色だと分かりづらく感じてしまうんですよね
ピーナッツさん
こんばんは。
コメントありがとうございます。
実は私は蛍光ペンで引くのは
あまりお薦めしません。
台本に書かれている全てが情報で、
その情報は読んでいる時期によっても
大切だと思う気づきはそれぞれです。
「最初は重要だとは思わなかったけど、
これって重要だな」
と思う箇所はきっと出てくると
思うのです。
一度蛍光ペンで引いてしまうと、
そこが重要だと思う反面、
引いてないところは
無意識に重要でないという
いういうふうになり、
それが盲点となって
却って読み込みが難しくなるのですね。
ですので、
そういった盲点を出来るだけ外すためにも
蛍光ペンは引かないことをお薦めします。