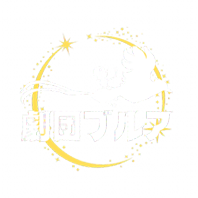相手役の演技を
際立たせる動作練習
私たち俳優は自分の表現だけではなく、相手の表現を効果的に生かすことも必要で、この演技方法があまり知られていません。例えば、よく「主役の前を横切るな」と演出の方が言われたりすると、主役の前を通ってはいけないとなり、ついつい後ろを通ることも経験された人も多いはず。しかしこの方法を使えば、主役の前を敢えて通った方が、主役の俳優にとって親切な演技方法になるのです。以前、主役の前を通るなとダメ出しを受けた俳優がこの技術を使って、再び前を通って芝居をした時、この件について演出からのダメ出しが来なくなって驚きましたという話もあります。後ろを通ることで役者の動機が現れてしまってはかえって物語の世界に入る邪魔になる。俳優の前を横切るなというルールは存在しないのです。※この内容の関連ブログはこちらをタップ※
共演者の演技を
生かす演技練習
前から見てどうすれば絵になるか、そして意図通りの表現が成立するかを共演者の演技も踏まえた演技練習をしています。共演者が出来るだけ客席側に顔を持っていけるように誘導していく演技方法の一例です。
客観的な視点から
作る演技練習
登場人物のそれぞれの演技プランで動きをつけると前から見てどういう風に見えるのかをイメージングする練習。一人一人の演技のプランを別々に実際にやってみて、それが組み合わさった時のそのシーンを想像しながら演技する。これで、今自分がしている表現は『相手との兼ね合いでこのように見えているんだ』と客観的な動きを意識してできるようになるのです。演技は自分だけで感情を入れれば出来るというものではなく、舞台美術、照明、音楽、相手の俳優を含めたビジョンを考えたものでなければなりません。練習を前から見ることによって客観的な意識を持つことが非常に大切なのです。
位置取りを考えて
相手を見せる練習
不器用な男が女性のお遣いを自ら買って出て人助けをするワンシーン。わざと相手の前を通って相手の演技や顔の仕草をお客さんに自然に見てもらう方法を説明している稽古風景です。左側に位置取りできる芝居を考えた方が相手の芝居が生きるのですという説明をしています。右側から手助けすると相手は前を向く機会がなくなるので、動作を起こした自分に目が行ってしまうのですが、この方法だと動作を起こしている人よりもじっと静止している人が自然と見られるようになるのですね。余談ですが、不器用な男の表現は女性が遣いの紙を奪い取る時、音を立てて取るのもポイントです。視覚だけでなく聴覚にも表現を入れて、観る側のイメージを膨らませるのが演技者の仕事です。
話芸の練習
日本の話芸。七五調練習。節と啖呵(たんか)を覚えて挑戦してみてます。この話し方、日本人には馴染みがあり、心に入りやすい調子でもあるので、現代演劇の俳優陣も絶対に押さえておきたい技術ですね。しかしこれがなかなか難しいのです。
話芸の練習番外編
話芸の練習は基礎練習後にやらないと声帯を傷つける怖れがありますのでご注意ください。このように話が自在にできると結構気持ちが良いのですよ。身体の動作から感情を誘発する観点から言うとこのような声を出す練習はストレスの発散や、気持ちの高揚にも十分使えるので、多くの方にこういう演劇の練習を経験していただきたい。何より楽しいのです。
発声から感情誘発させる練習
息の吸い方で、自然と感情が誘発させている方法。台詞途中の震えるような声、目線などは『息』のスイッチによって生まれている。